電験3種 各科目の解説
基本単位・組立単位・接頭語・次元解析をまとめて整理
電験三種の勉強するとき、特に計算をしているときに単位を意識していますか?
単位はおろそかにしがちな部分ですが、単なる記号ではなくとても大切な表記なんです。
単位が分かればその計算が間違っていないかを判断できますし、理論科目の問題として単位に関する問題が出題されることもあります。
ここでは電験三種の理論を理解する土台として、SI単位・接頭語・次元解析についての解説をして、「式の意味を単位から読み解く力」を身につけることを目指します。
この記事で解説する内容の全体像と結論
この記事では、電験三種の理論科目を学ぶうえで必須となる「単位まわり」の3本柱を整理します。
- SI単位(国際単位系)の基本構造
長さ[m]、時間[s]、質量[kg]、電流[A]といった基本単位から、電圧[V]、抵抗[Ω]、電力[W]などの組立単位がどう作られているかをイメージでつかみます。 - 接頭語(k, M, m, μ など)の正しい感覚
「kV」「mA」「μF」「mm²」などで、10の何乗が掛かっているのかをきちんと意識できるようにします。特に、平方メートルや立方メートルで「2乗・3乗がどこに掛かるか」のつまずきを丁寧に整理します。 - 次元解析(単位チェック)で式を検算する力
数値を入れる前に単位だけを見て、「この式の形はおかしくないか」「この変形は正しいか」を自分でチェックできるようにします。
結論として、次の3点を理解することが、理論科目全体の理解を大きく楽にします。
- 物理量は「数値 × 単位」のこと。
- 接頭語は「10の何乗か」を表す記号のこと。
- 式の両辺では「単位(次元)が常に揃っている必要がある」こと。
単位と物理量、接頭語・次元解析の基礎
物理量と単位とは何か?
「物理量」というのは、「測れる量」のことです。たとえば、
- 電圧:12 V
- 電流:3 A
- 抵抗:4 Ω
というとき、
- 「12」「3」「4」は数値
- 「V」「A」「Ω」は単位
です。
一般的には $$物理量=数値×単位$$
という形で表されます。
電験3種の計算問題で導く電流、電圧、電力などはこの物理量です。
基本単位と組立単位
単位には基本単位と組立単位の2種類があります。基本単位は「これ以上分解できない基本の単位」です。
基本単位には次の7つがあります。
| 物理量 | 単位名 | 記号 |
|---|---|---|
| 長さ | メートル | m |
| 質量 | キログラム | kg |
| 時間 | 秒 | s |
| 電流 | アンペア | A |
| 熱力学温度 | ケルビン | K |
| 物質量 | モル | mol |
| 光度 | カンデラ | cd |
そして組立単位とはこれらの基本単位を掛け算・割り算して、組み合わせた単位のことです。
実は単位も数値と同様に掛け算や割り算ができます。そして基本単位が決められた組み合わせになると、組立単位となり専用の名前に変わります。
例えば多くの皆さんがご存知であろうV(ボルト)も組立単位です。V(ボルト)を基本単位で表すと次のようになります。
V=kg・m2/(s3・A)
例として電験3種でよく出てくる組立単位を以下に挙げます。
- J(ジュール)
- N(ニュートン)
- W(ワット)
- C(クーロン)
- A(アンペア)
- V(ボルト)
- Ω(オーム)
- F(ファラド)
- H(ヘンリー)
- T(テスラ)
- Wb(ウェーバ)
これらの組立単位は単なる基本単位の組み合わせとしてみると覚えるのが大変です。ですがその単位の意味を理解するとイメージもしやすく覚えやすいです。
各単位の意味とどの基本単位の組み合わせでできているかはこちらの記事で解説していますので、併せて読んでみてください。
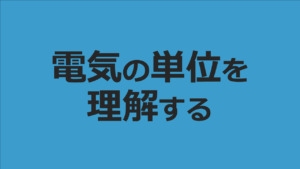
接頭語(k, m, µ など)の考え方
接頭語とは、単位の前について、その量が「10の何乗倍か」を表す記号です。
電験三種で特によく出てくるものをまとめると次のようになります。
| 倍率 | 読み方 | 記号 |
|---|---|---|
| 1012 | テラ | T |
| 109 | ギガ | G |
| 106 | メガ | M |
| 103 | キロ | k |
| 10-3 | ミリ | m |
| 10-6 | マイクロ | μ |
| 10-9 | ナノ | n |
| 10-12 | ピコ | p |
ここで注意したいのがアルファベットの大文字と小文字とで意味が変わるということです。例えばmとMは同じエムですが、ミリとメガとそれぞれ意味が違います。
単位や接頭語を使うときは小文字と大文字の区別をきちんとしましょう。
次元解析とは何か
次元解析とは、「式の両辺の単位(次元)がそろっているかどうか」を調べることで、その式が物理的におかしくないかを確認する方法です。
電験では方程式を解いて答えを出す問題がよく出ます。方程式は左辺、右辺にそれぞれ数値を当てはめて解いていきますが、この左辺と右辺の単位(次元)は必ず一致します。
ここが一致していなければ、どこか計算が間違っているということです。
次元解析の考えは、正確に計算をするためにも重要ですし、電験では次元解析に関する問題が出題されることもあります。
オームの法則を例に次元解析してみる
例としてオームの法則で次元解析の具体的な考え方を学んでいきましょう。
オームの法則:$$ V=IR $$
これを単位にすると、
$$ [V]=[A]⋅[Ω] $$
となります。ここで[A]と[Ω]を基本単位で表すと
$$ [V]= \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-1} $$
$$ [Ω]=\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-2} $$
となります。右辺を計算すると、
$$ [A]⋅[Ω]=\text{A} \cdot (\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-2}) = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-1} $$
となり、左辺の[V]を基本単位で表したものと一致します。
このように左辺と右辺で単位に不一致が無いかを確認するのが次元解析の基本的な使い方です。
よくある勘違い・つまずきポイントの解説
ここからは初学者が勘違いしやすかったり、つまずきやすいポイントについて解説をします。
接頭語と2乗・3乗がごっちゃになる
例えば面積を表すcm2は接頭語のcと単位のm両方に2乗したものです。これを単位だけが2乗されると勘違いする人が結構多いです。つまり、
$$\mathrm{cm}^2 は 10^{-2}~\mathrm{m}^2 $$
と思ってしまう勘違いです。
しかしこれは接頭語と単位の両方に2乗がかかります。ですので
$$ 1 cm^2 = (10^{-2}~\mathrm{m})^2 = 10^{-4}~\mathrm{m}^2 $$
となります。
異なる単位の物理量は加減算できない
単位は掛け算、割り算ができますが、足し算引き算はできません。
これは物理量を考えれば納得の行く話かと思います。
例えば長さ(メートル)と重さ(kg)の足し算は成り立つでしょうか?
普通に考えてできなさそうと思いますよね。
物理量の計算をするときの大事なルールとして、
- 加減算(+、−)できるのは、単位(次元)が同じものだけ
というのがあります。
電験三種の計算で、式を立てたあとに、異なる単位を足し算引き算しているようであれば、何かが間違っているということです。
簡単な確認問題(2問)
確認問題1:接頭語と二乗
次の値を \( \mathrm{m}^2 \) の形に直してください。
(1) \( 3.0\ \mathrm{cm}^2 \)
(2) \( 5.0\ \mathrm{mm}^2 \)
【解説】
\( 1\ \mathrm{cm} = 10^{-2}\ \mathrm{m} \) なので,
$$
3.0\ \mathrm{cm}^2
= 3.0 \times (10^{-2}\ \mathrm{m})^2
= 3.0 \times 10^{-4}\ \mathrm{m}^2
$$
同様に,\( 1\ \mathrm{mm} = 10^{-3}\ \mathrm{m} \) なので,
$$
5.0\ \mathrm{mm}^2
= 5.0 \times (10^{-3}\ \mathrm{m})^2
= 5.0 \times 10^{-6}\ \mathrm{m}^2
$$
ここでのポイントは,
$$
(10^{-2})^2 = 10^{-4}
$$
$$
(10^{-3})^2 = 10^{-6}
$$
のように,「接頭語(10 のべき)の指数も 2 倍される」ということです。
確認問題2:単位から式をチェックする
ある回路で,電圧 \( V\ [\mathrm{V}] \),電流 \( I\ [\mathrm{A}] \),抵抗 \( R\ [\Omega] \) の間に次の関係式があるとします。
$$
V = IR
$$
$$
P = VI \qquad (\;P\ は電力\ [\mathrm{W}]\;)
$$
(1) と (2) から,電力 ( P ) の単位を「基本単位(\( \mathrm{kg},\ \mathrm{m},\ \mathrm{s},\ \mathrm{A} \))」で表してください。
【解説】
抵抗の単位は
$$
[\Omega] = \frac{[V]}{[A]}
$$
電力の単位は
$$
[P] = [V][I] = \mathrm{V} \cdot \mathrm{A}
$$
ここで,電圧 ( V ) を基本単位に分解します。
エネルギー ( J ) の単位は
$$
[J] = \mathrm{kg}\ \mathrm{m}^2\ \mathrm{s}^{-2}
$$
電荷 ( C ) の単位は
$$
[C] = \mathrm{A}\ \mathrm{s}
$$
したがって電圧は
$$
[V]
= \frac{[J]}{[C]}
= \frac{\mathrm{kg}\ \mathrm{m}^2\ \mathrm{s}^{-2}}{\mathrm{A}\ \mathrm{s}}
= \frac{\mathrm{kg}\ \mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^3\ \mathrm{A}}
$$
よって電力の単位は
$$
[P]
= [V][I]
= \frac{\mathrm{kg}\ \mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^3\ \mathrm{A}} \times \mathrm{A}
= \frac{\mathrm{kg}\ \mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^3}
$$
となります。
これが「ワット \( [\mathrm{W}] \) を基本単位で書いた形」です。
過去問演習(理論科目 令和5年度 下期 問14)
それでは最後に実際の過去問を解いて、理解の定着を図りましょう。令和5年下期の問14で出題された問題を取り上げます。
問題文
固有の名称をもつ SI 組立単位と,この単位と同じ内容を表す他の表し方との組合せとして誤っているものを,次の (1)〜(5) のうちから一つ選べ。
SI 組立単位の記号 : SI基本単位及びSI組立単位による他の表し方
- (1) F : C / V
- (2) W : J / s
- (3) S : A / V
- (4) T : Wb / m²
- (5) Wb : V / s
各単位が「何を表すか」をイメージで整理する
まず、この5つの単位がそれぞれ「何を表す量か」「どんな状況で出てくるか」を言葉で押さえておきます。
(1) F(ファラド):どれだけ電気をためられるか
ファラド F は「静電容量(キャパシタンス)」の単位です。
- コンデンサに電圧 V をかけたとき、どれだけの電荷 Q(クーロン)をため込めるか
を表す量が静電容量 C です。
イメージとしては、「同じ 1 V を加えたときに、より多くの電荷をため込めるほど容量が大きい」という感じです。
例えば:
- 1 F のコンデンサ:1 V かけると 1 C の電荷を貯められる
- 100 µF のコンデンサ:1 V かけると \(100\times10^{-6}\) C の電荷を貯められる
このように電圧あたりに何クーロン貯まるかを測る、器の大きさのようなものです。
公式と単位の関係
静電容量 C の定義式:
- \( Q = CV \)(蓄えた電荷 = 容量 × 電圧)
ここから
- \( C = Q/V \)
となるので、単位は
- \([F] = [C] / [V] = C / V\)
したがって、(1) の「F:C/V」は正しい組合せです。
(2) W(ワット):どれくらいの速さでエネルギーを使うか
ワット W は「電力」の単位です。
- 電力は「単位時間あたりにどれだけエネルギーを使う(または送る)か」を表します。
- 言い換えると、「エネルギーの使い方の速さ」です。
例:
- 100 W の白熱電球:1 秒あたり 100 J のエネルギーを消費する
- 1 kW の電気ヒーター:1 秒あたり 1000 J のエネルギーを熱として出す
1 秒あたりのエネルギー消費が大きいほど、電力(W)の値が大きくなります。
公式と単位の関係
電力 P の定義:
- \( P = W/t \)(エネルギー W を時間 t で割ったもの)
ここで W の単位は J(ジュール)、t の単位は s(秒)なので、
- \([P] = [J]/[s] = J/s\)
したがって、(2) の「W:J/s」は正しい組合せです。
(3) S(ジーメンス):どれくらい電流が「流れやすいか」
ジーメンス S は「コンダクタンス」の単位です。
抵抗 R [Ω] が「流れにくさ」を表すのに対して、
- コンダクタンス G [S] は「流れやすさ」を表します。
イメージ:
- 抵抗 R が小さいほど、同じ電圧でたくさん電流が流れる
- その「流れやすさ」の度合いがコンダクタンス G
例えば:
- 1 S の素子:1 V かけると 1 A 流れる(とてもよく流れる)
- 0.1 S の素子:1 V かけると 0.1 A 流れる
公式と単位の関係
コアになる式は 2 つです。
- オームの法則:
- \( V = IR \)
- ここから \( R = V/I \)
- コンダクタンスの定義:
- \( G = 1/R \)
- よって \( G = I/V \)
この \( G = I/V \) から、単位は
- \([S] = [I]/[V] = A/V\)
となります。よって、(3) の「S:A/V」は正しい組合せです。
(4) T(テスラ):1 ㎡あたりにどれくらい磁束が通っているか
テスラ T は「磁束密度」の単位です。
- 磁束密度 B は、「ある面積をどれだけ磁束(磁界の線)が通り抜けているか」を表します。
- イメージとしては、「単位面積あたりの磁界の濃さ」「磁界の密度」です。
例えば:
- B が大きいほど、その場所の磁界が強い(コイルに流れる誘導電流も大きくなりやすい)。
- 同じ磁束 Φ でも、その磁束が通る面積が大きければ B は小さくなり、小さな面積に集中すれば B は大きくなります。
公式と単位の関係
磁束 Φ [Wb]、磁束密度 B [T]、面積 S [m²] の関係は
- \( \Phi = B S \)
なので、
- \( B = \Phi / S \)
単位で書けば、
- \([T] = [Wb]/[m^2] = Wb/m^2\)
したがって、(4) の「T:Wb/m²」は正しい組合せです。
(5) Wb(ウェーバ):磁界の「総量」「束の本数」
ウェーバ Wb は「磁束」の単位です。
- 磁束 Φ は、ある面を通り抜ける磁界の「総量」「束の本数」のようなイメージです。
- 例えば、磁束密度 B が一定のとき、面積が広いほど Φ は大きくなります(たくさんの「磁界の線」が通る)。
- 逆に、同じ B でも面積が小さければ、Φ も小さくなります。
電験では特に、
- コイルを貫く磁束が時間とともに変化するとき
- その変化の速さに比例して誘導起電力(V)が生じる
という関係(ファラデーの法則)で頻出です。
公式と単位の関係
ファラデーの電磁誘導の法則(単純な形)は
- \( e = -\frac{d\Phi}{dt} \)
です。単位だけ見ると、
- \(e\) の単位:V
- \(\Phi\) の単位:Wb
- \(t)\ の単位:s
なので、
- \([V] = [Wb]/[s]\)
ここから、
- \([Wb] = [V] \cdot [s]\)
となります。
つまり、「1 Wb の磁束が 1 秒で 1 V の起電力を生む」といったイメージです。
したがって、正しい関係は
- Wb = V・s
であり、選択肢 (5) のような
- Wb = V / s
ではありません。
解答
以上の通り、誤っている組み合わせは(5)ですので、正解も(5)になります。
解答手順のまとめ
- 各単位が「何を表すか」「どんな場面で出てくるか」をイメージする。
- その物理量の「定義式」を思い出す。
- 定義式から単位の関係を導く。
- 与えられた組合せと比較し、合っているか・向きが逆になっていないかを確認する。
この問題から得ておきたい視点
- 単位は「記号」ではなく、「何をどのくらいの速さで・どれくらいの濃さで・どれだけためるか」を表す「意味のある言葉」であること。
- 各組立単位について、「1 ○○ とは、1 △△ を 1 □□ したときの量」と日本語で説明できるようにしておくと、公式や単位の向きを間違えにくくなります。
- 例:
- 1 W:1 秒あたり 1 J のエネルギーを使う
- 1 F:1 V かけたとき 1 C の電荷を蓄える
- 1 S:1 V かけたとき 1 A 流れる「流れやすさ」
- 1 T:1 m² あたり 1 Wb の磁束
- 1 Wb:1 秒あたり 1 V を生むような磁束変化の大きさ
- 例:
- 単位をここまで言葉で説明できるようになると、単位問題に限らず、理論全体の「式の意味」がかなり見えやすくなります。
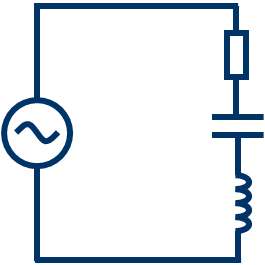

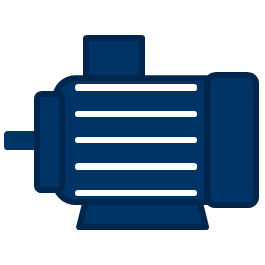
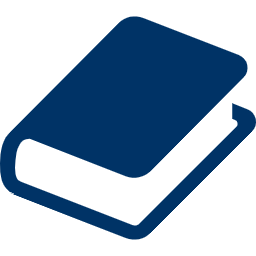
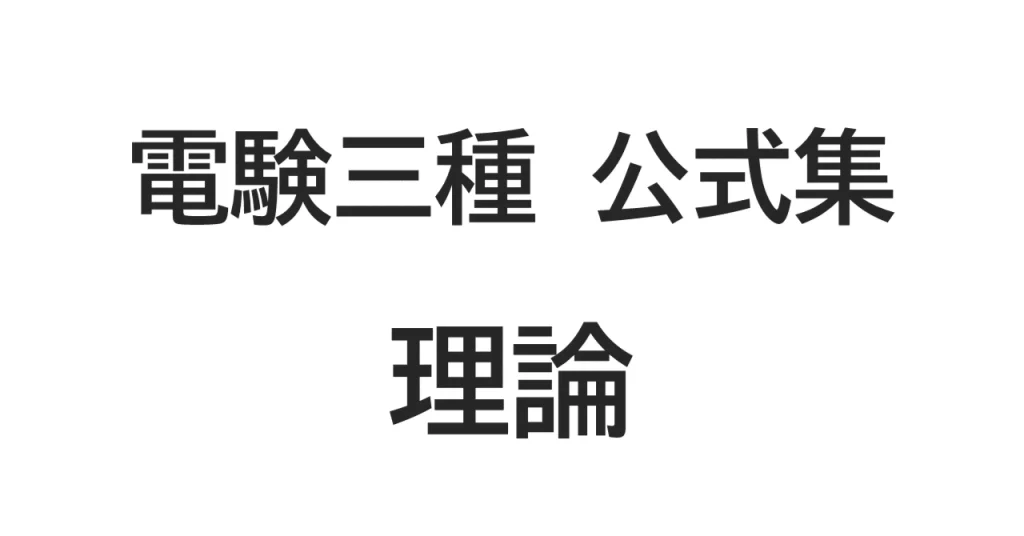
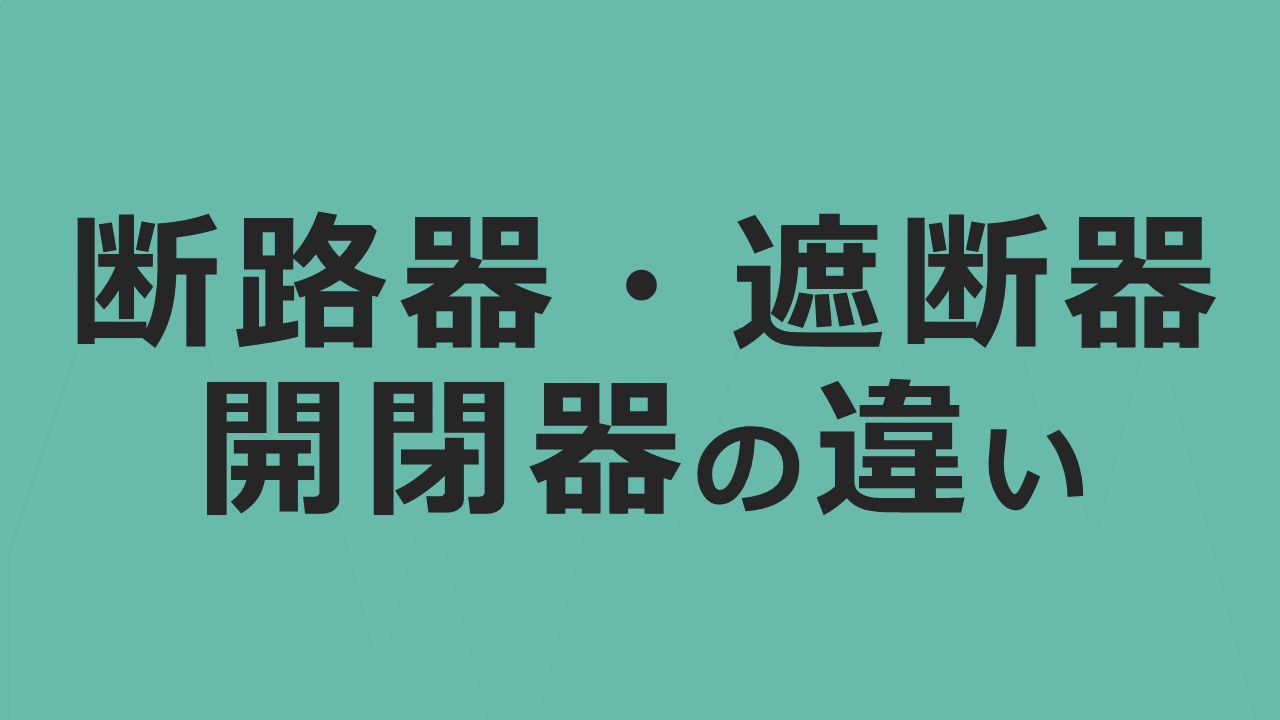
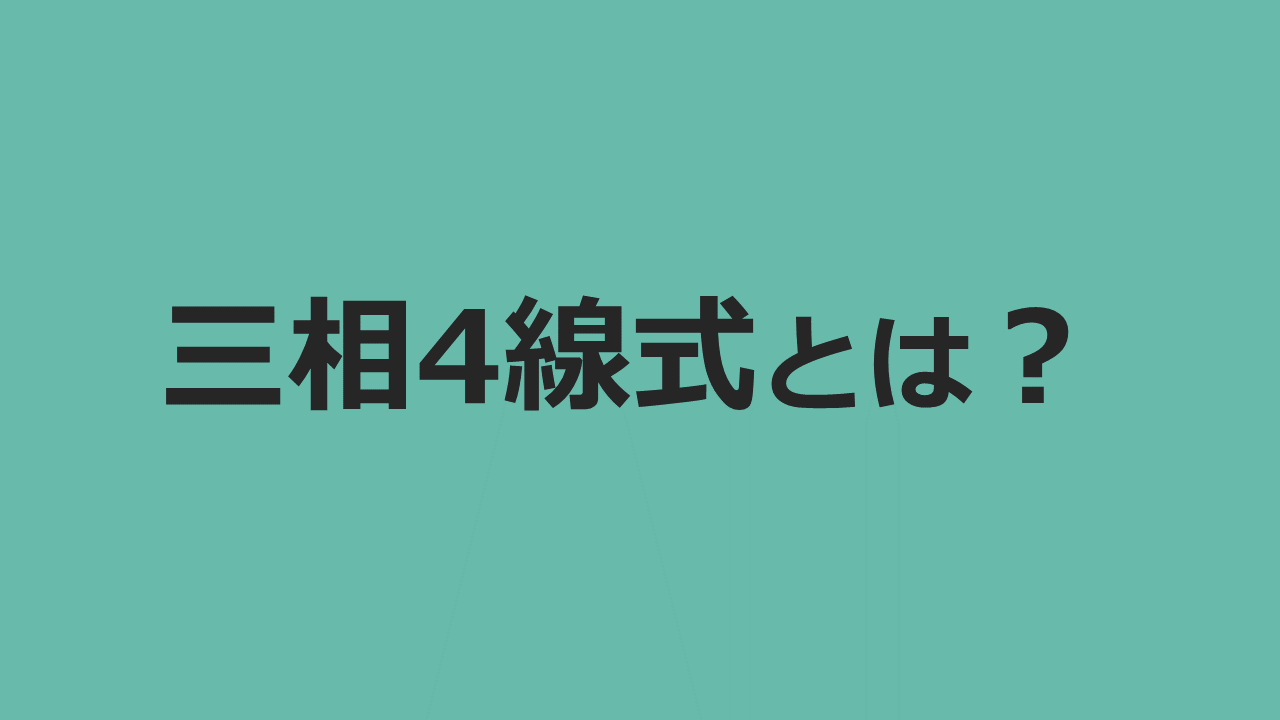
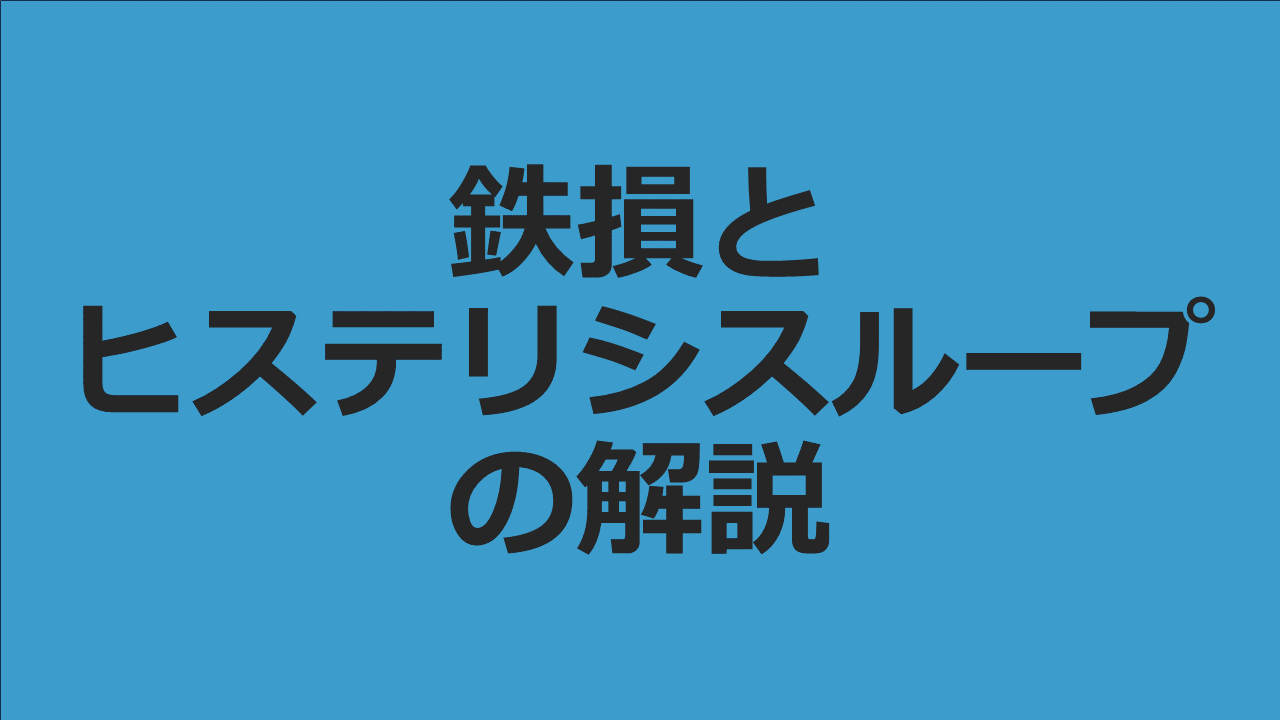
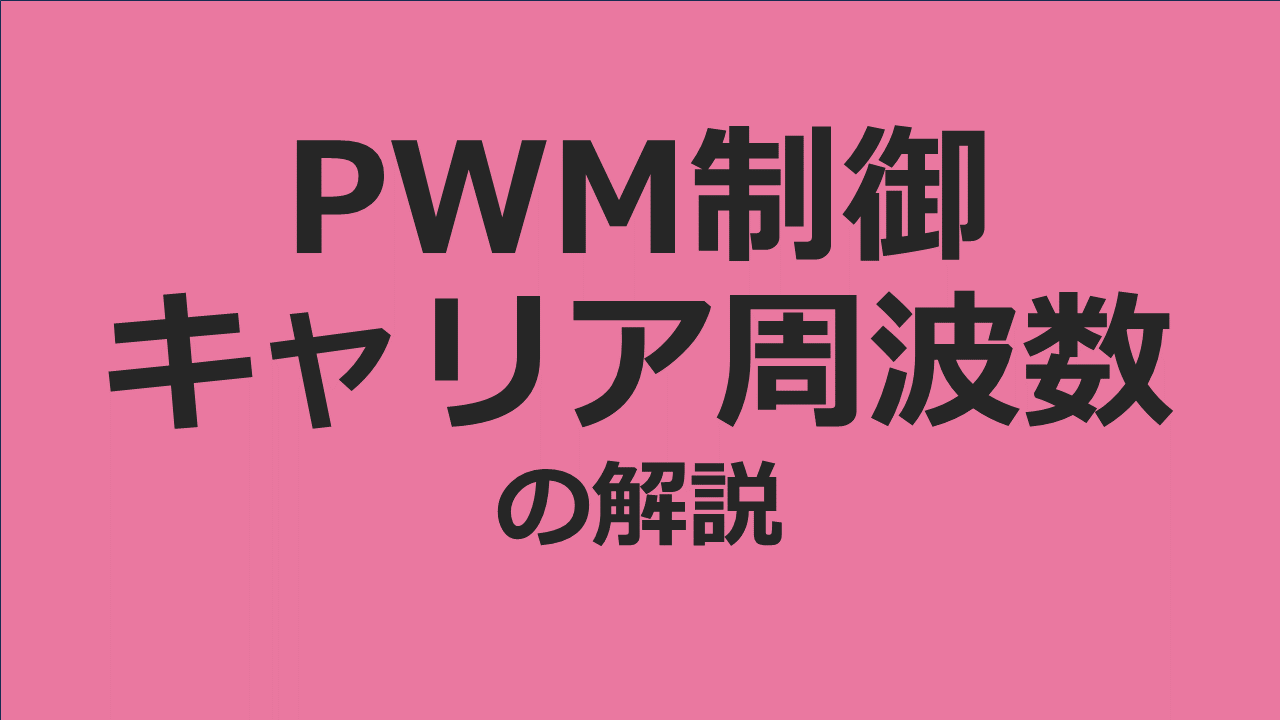
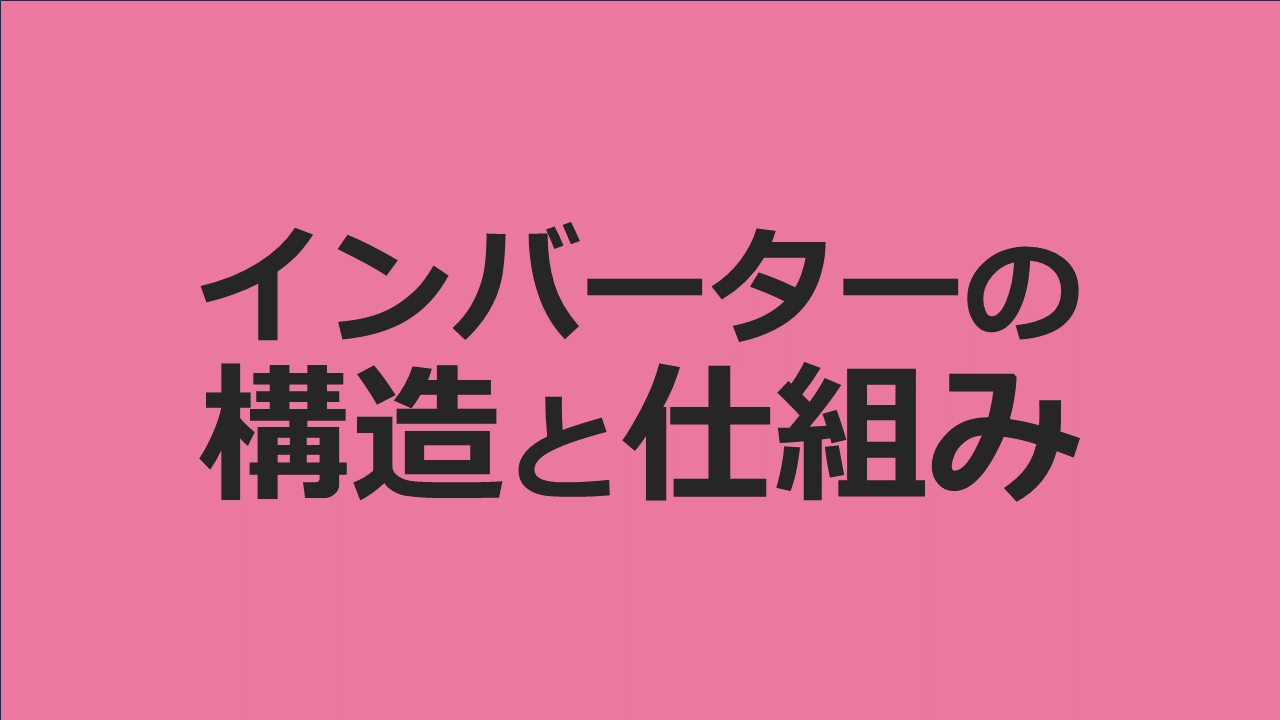
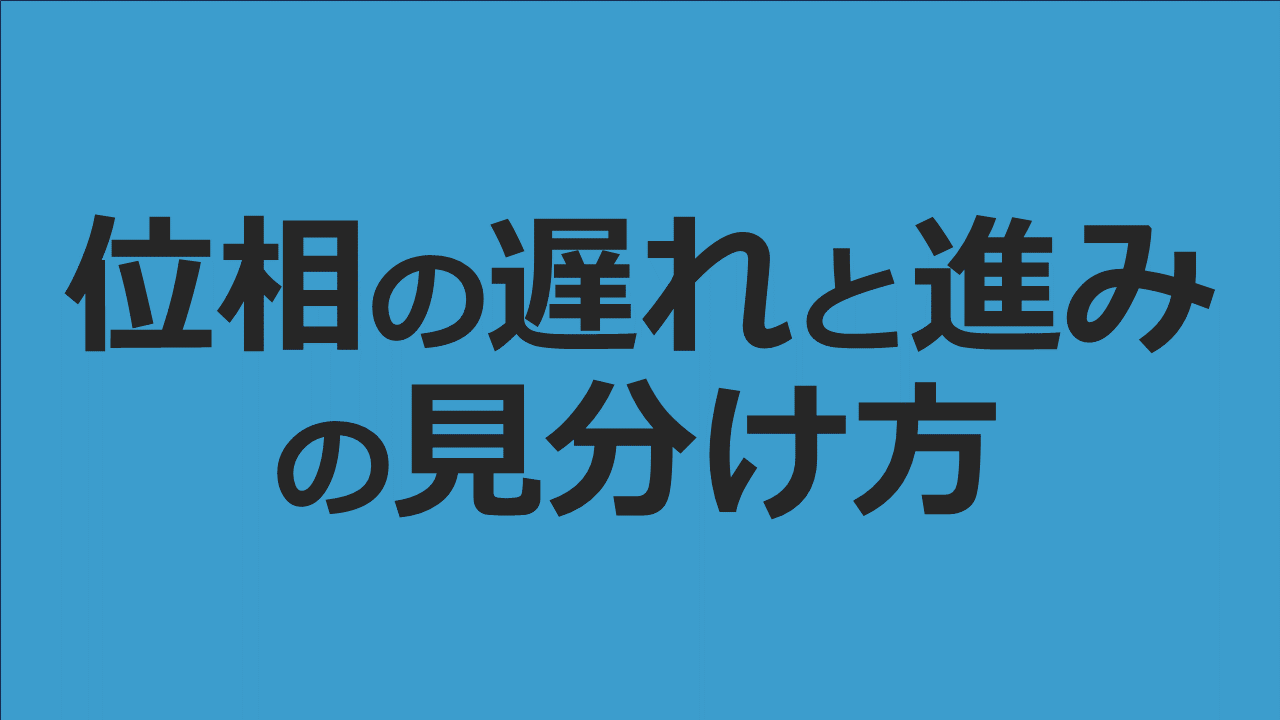
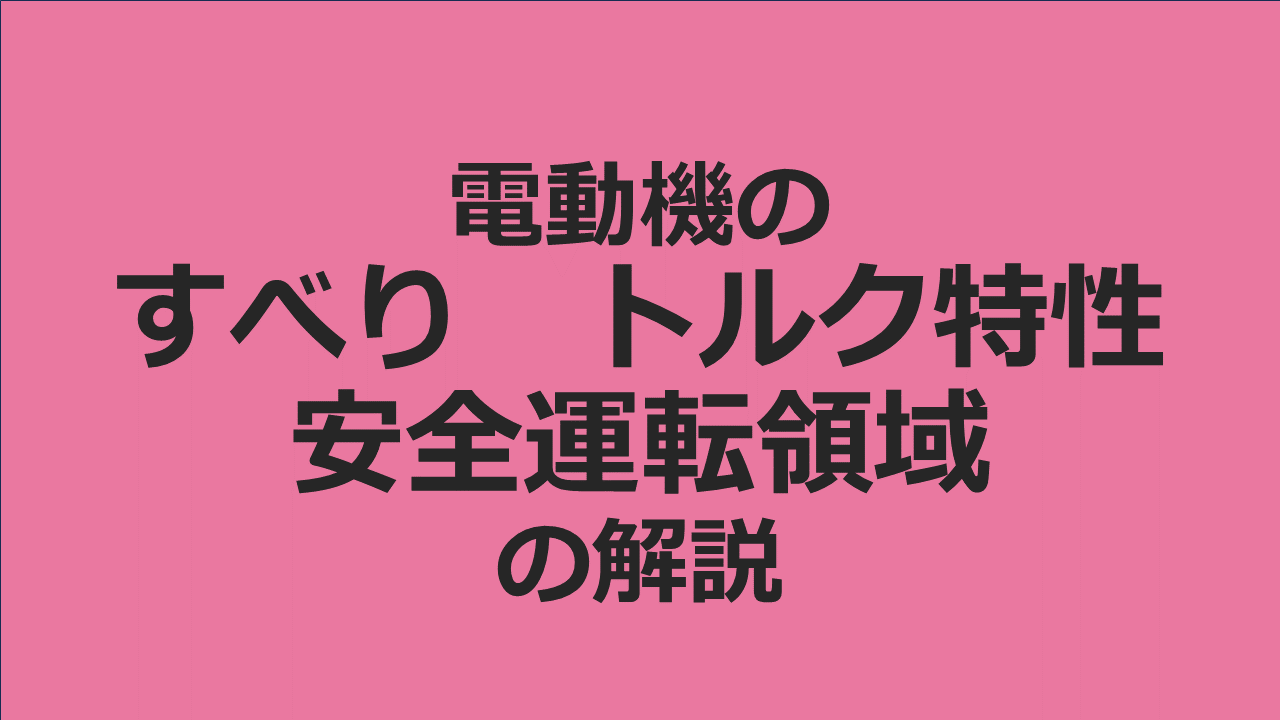

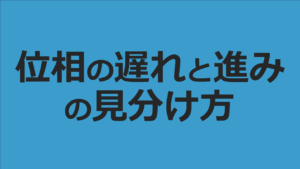

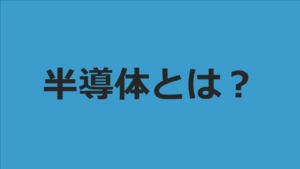
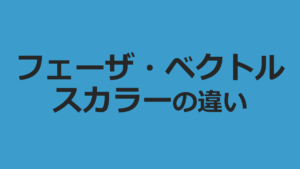
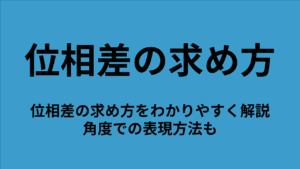
コメント